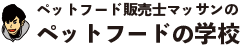目次
犬の飼育頭数減少の原因はブリーダーの減少
猫の今後を考えて行く上で犬を取り巻く環境を見ていきましょう。

犬は飼育頭数がどんどん減って、ついに猫よりも減ってしまったみたいですね。
犬の飼育頭数が減ってしまった一番の理由は動物愛護法改正による少数のみブリーディングしていたブリーダーの減少により、子犬の繁殖頭数が2004年から2014年までの10年間で45%も減ってしまったことと言われています。ブリーダーは72%も減少しています。

2006年法改正施工後1-10頭繁殖するホビーブリーダーは大幅に減った

そんなにですか!すると飼育頭数もまだ落ち込んでいくことが予想されますね。
2005年の第二次法改正、2006年の施行後にブリーダー激減
法改正時に子犬の繁殖数や繁殖回数は定義されていなかったものの、年2回の繁殖あるいは2頭以上の子犬を繁殖すれば営利目的のためにブリーダー業を行っていると解釈されていました。
この解釈がブリーダー業の定義として地方自治体のサイトに定義として掲載されため、ブリーダー「業」(動物取扱業1種)として見なされた場合は地方自治体への登録・許可が必要だったことから、1~10頭程度と少ない繁殖を行っていた(便宜上ホビーブリーダーとも言われる)ブリーダーが辞めていくことになりました。

少ない繁殖を行っていたブリーダーさんにとっては動物取扱業1種が重荷だったんですね…
「生活するほどの営利目的ではないから、登録するほどじゃない」という感じの層が多かったのではないかなと。私の予想でしかないですが。
犬の価格は上がり続けています
こうして子犬の市場への供給量が減り、値段は2010年から2016年で3倍に上昇し、まだ上がり続けています。
価格決定のメカニズムとしては、いずれ生産量と価格(コスト)のバランスが取れるところで落ち着くので、犬の価格も落ち着くことが考えられますが、それはまだ今ではないようです。

子犬が減って値段が上がれば飼育する人が減るのは当然ですよね。
それに加えて高齢化が進み、新しく飼育することができない家庭が増えました。更に三世代世帯は減り、単独世帯と夫婦のみで共働きの家庭が増えたことで、犬の飼育に踏み切れない家族が増えてきています。
犬と猫の入手経路の違い
ここで大きな違いが出てくるところが犬と猫の入手経路の違いです。
子犬は73%が「ペットショップかブリーダー」から入手していますが、子猫は85%が「もらった、拾った、迷い込んできた」となっており、供給方法が全く違っています。

こんな時代でも「もらった、拾った」が多いんですね!
犬は狂犬病があるため、野良犬を見ることはほとんどなくなったのではないでしょうか。こうして猫は供給自体は増えてはいないものの、減ってもいないため、飼育人数は一定を保つ要因のひとつとなっています。
犬猫を高齢者への譲渡を制限している自治体は少なくない
「購入しなくても自治体から譲渡を受ければいい」と考える方もいらっしゃると思います。しかし犬、猫ともに高齢者への譲渡を制限している自治体は少なくなく、早いところで60歳以上、多くのところで65歳以上が制限をされています。
例えば東京の場合は61歳以上で「家族からの継続飼育の同意または同意書・誓約書があれば譲渡可」としています。

そんな制限があること全く知りませんでした…
三世代世帯が減っている中、こうした条件を満たすのは難しいことであり、また20年以上生きることもある犬猫を考えれば、自身の年齢を考えるとそこまでして飼育するとはならない現状があります。
今後の犬猫を取り巻く環境
ペット可物件というだけでなく、「ペット共生」マンションなどペットと暮らす環境は、以前と比べれば整ってきているにも関わらず、ファミリー世帯が減少し、子犬数も減り、価格も上がり、飼育へのハードルは上がるばかりです。
飼育者数が減れば置き去りや遺棄、虐待などといった問題が減るという一方で、共生するための環境が作りにくくなったり、需要と供給のバランスからフードやシーツなどの価格にも変動が起こる可能性は十分にあります。
猫だけで考えれば飼育頭数が増えていることもあり、猫業界へ参入する企業が増えることも考えられ、アイテムが豊富になったり、猫にとってはいい変化が生まれることも考えられます。

供給が増えて安くなるのか、売れないから製造を制限して高くなるのか…
犬猫を取り巻く環境はまだ大きく変化はないと考えられますが、犬同様に血統の猫の数の減少や価格高騰が考えられます。
その他に、散歩など手が掛からない猫は夫婦世帯でも飼育することが可能であり、子どものように接する家庭は今よりもまだまだ増えていくことが考えられます。
しかし猫は爪を研ぐという考えから、アパートマンションでの飼育は敬遠されがちで、今後どのように変化していくかは観察の必要がありそうです。
また動物の飼養は高齢者の健康に寄与すると考えられ、医療面での社会経済的価値が考えられています。実際に多額の医療費削減に繋がっている国もあり、健康効果への研究が進んでいくと思われます。
犬猫共に飼育数の変動によって影響もあると思いますので、今後は飼育の環境や考え方が変わってくるのではないでしょうか。
まとめ
- ブリーダーの減少が犬の飼育頭数減少の原因
- 子犬の減少により価格高騰
- 猫の飼育数は増えていないものの減っていない
- 猫の入手経路の85%が「もらった、拾った、迷い込んできた」
- ペットとの共生社会について考えていく必要あり
- 動物飼育が人間の健康に寄与するという結果あり

今後も犬猫の飼育環境が大幅に変化することはまだなさそうですが、犬の飼育頭数、飼育家庭の減少が及ぼす影響は小さくなさそうです。愛猫、愛犬を大切にし、いつまでも一緒に暮らせるような環境作りをしていきたいですね。