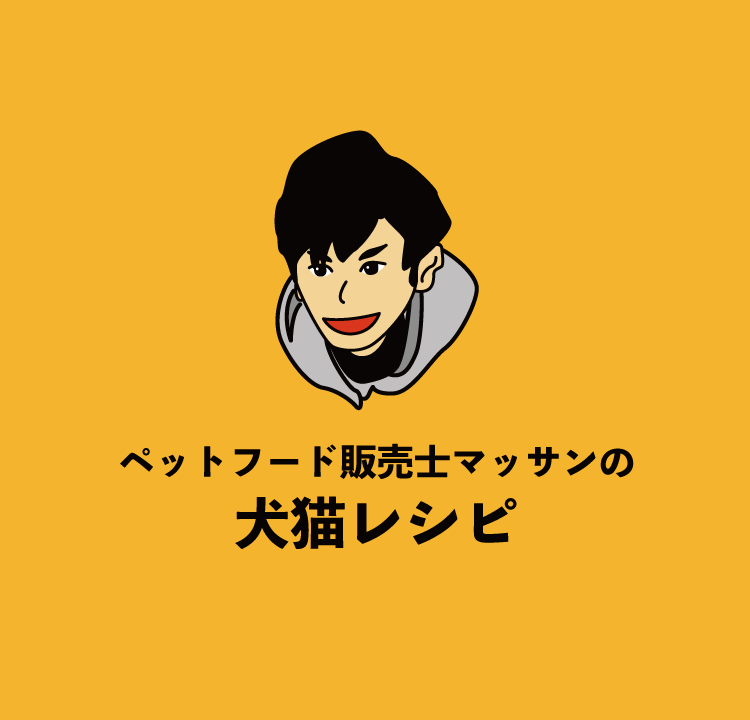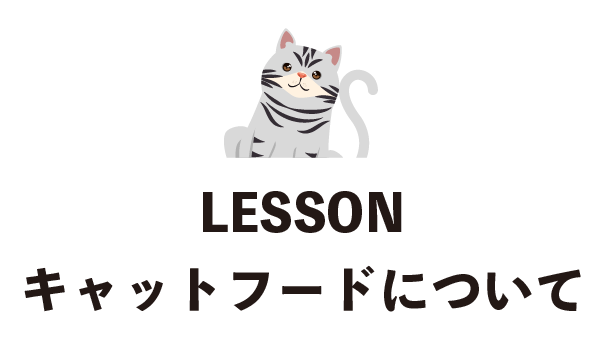キャットフード・ドッグフードの安全性を確かめる項目

キャットフード・ドッグフードの安全性の見分け方について解説してもらいました!安全性は大きく分けて以下の5つの項目から判断するとわかりやすいようです。
- 原材料
- 製造環境
- 輸送方法
- 保管状況
- パッケージ
原材料について
原材料について
- オーガニック食材
- 人用の品質の食材
- 主に人が食べる可食部をのぞいた食材(魚の血合いなど。)
- ミートミールなどどの動物を使ったかわからない食材
オーガニック食材
一番安全性が高い食材はオーガニックで作られた農産物です。農薬を使用していないオーガニック食材は人用、動物用など用途もわかれていないので価格が高くなります。
農薬にアレルギーがある犬猫もいますので、そういった場合には良い選択肢になると思います。
人用の品質の食材
スーパーなどで販売されている野菜や、大きさの規定などで出荷できなかった野菜、虫食いで出荷できなかった野菜などといえばイメージが付きやすいかと思います。
人用として出荷せず、ペットフード用として出荷されたものという違いだけですので、原則違いはありません。
主に人が食べる可食部をのぞいた食材
人が食べる部位を取り除き、人にあまり人気がない部位を残した食材です。
これも決して人が食べられないわけではなく、人気がなかったり、需要の低い部分です。
魚の血合い部分や、お肉の切れ端、内臓などがあります。血合いや内臓などは栄養も豊富なので、ペットフードに適した食材です。
ミートミールなどどの動物を使ったかわからない食材
ミールは原材料を粉にした状態のことをいいます。
衛生面や栄養として問題があるといったことではありませんが、ミートミールという表記の場合はどの種類の動物を使ったかわからないため注意が必要です。
原材料が明確なものは、例えば鶏を使用したものであれば家禽ミール、豚ならポークミール、魚ならフィッシュミールというように食材がわかるようになっていますので、こうした表記のものを選ぶこともひとつの対策になります。
各国の農薬の使用制限
農薬についてはどこの国も人にとって問題がない量を規定していますが、国によって若干の違いがあります。
EU圏は農薬の使用制限が厳しく、残留農薬についても規定されていることから、食材の安全性は高い地域と言えます。
日本は高温多湿のため、どうしても防除の必要性が高く、農薬量は欧州圏と比較すると多い傾向にあります。
酸化防止剤、防腐剤
BHT、BHA、エトキシキン、没食子酸プロピルなど、発ガン性、変異原性、催奇形性が認められていたり、疑われている成分の使用も判断材料のひとつです。
変異原性とは染色体など遺伝子情報に変化を起こす可能性です。催奇形性とは奇形の原因となる可能性です。
ただし上記の記事の通り、BHAは犬猫のように前胃がない動物には発がん性の兆候は見られないとされていますので、盲目的に危ないと決めつけないように注意しましょう。
着色料
着色料には赤色102号や赤色106号、黄色5号、青色1号にはアレルギーや染色体異常、喘息などを招く可能性があり、赤色106号に至っては日本以外の国では使用が禁止されています。
調味料など使う必要のないものは避けてもいいでしょう。

どんなにいい工場でも、管理方法がよくても原材料の品質が悪ければ意味がないということですね。
製造環境について
ペットフード大量リコール事件
今現在私が確認したペットフード工場で危険性を感じた工場はありませんが、2007年には日本のペットフード安全法を施行するきっかけになった「ペットフード大量リコール事件」がありました。これは北米最大のペットフードOEMメーカーが、中国の詐称された原材料を使用したことで大量の犬猫死亡事故を引き起こした事件です。
その詐称に使用したのはプラスチックのお皿などを製造する時に使う原材料のメラミンです。
国際基準を取得している工場がおすすめ
これ以降自社工場を建設して製造をしたり、管理体制を見直すなど各社で対応を行い、日本では国としてペットフード安全法を施行するに至りました。また中国の原材料は使用していないと明確に表示しているメーカーも多くあります。
こうして欧州やアメリカではSAIグローバルランクなどの国際規格を満たし、管理体制を第三者からも認められている工場が増えましたが、全ての工場が国際規格を満たしている訳ではありません。

消費者では調べられない点ですね。
製造工場を公開すると他社に商品を真似されてしまう可能性もありますし、企業秘密やレシピの問題などもあり、メーカーが公表しない限りは、表には出にくい部分です。逆に公表しているメーカーは自信の表れとも言えるかもしれません。
国際規格を取得している工場は一定の水準は確保されているのでおすすめです。
輸送方法について
ペットフードはひとつあたりが大きく重たいため、航空便などでは高くなりすぎるため、大量に運べて輸送費の安い船便の利用が一般的です。
船便で運ぶ場合はコンテナを使用するのですが、混載便と一本まるごとの輸送の二種類があります。そしてコンテナはドライコンテナとリーファーコンテナの二種類があります。
混載便とは
混載便とは、輸送量がコンテナ1本に満たない場合、他の人の荷物と一緒に1本のコンテナに混載する輸送です。コンテナ内の荷物は下ろす港もバラバラである場合が多いので、港に着く度に船から下ろされ、荷物の出し入れを行い、再度船に積み込まれます。場合によっては港で炎天下にさらされることになります。
また積み卸しがしやすいようにコンテナ船の上部に積まれることが多く、輸送時の温度変化が大きい可能性が高くなります。
こうして開け閉めや積載場所によって温度の上昇下降が激しくなると結露が起こり、最悪の場合はコンテナ内の湿度が非常に高くなります。
コンテナ一本まるごと輸送
コンテナ一本まるごとの場合は工場でペットフードを積込み、コンテナに封をします。この時点から日本輸入時に検疫を行うまでは開けることがありません。検疫は一部を確認するのみなので、厳密には日本の倉庫に到着するまで開けないと言ってもいい位です。
一本まるごとで開けることがないので、防湿剤で湿度対策を行い、エアバッグで荷物同士を保護し、航路が長い場合にはGPS付き温度計を入れておくことで温度変化の管理、チェックを行います。
ヨーロッパから日本への輸送では下ろすのも最後の方なので、温度変化の少ない船の下の方に積まれやすくなります。ただしシンガポールなど寄港した港の積み替えでコンテナの場所は移動します。
ドライコンテナとは
通常のコンテナです。動力は持たないので温度管理などは行わず、常温で運ぶコンテナです。例えば産業物資や雑貨、電子機器、ワインなど多くの貨物がドライコンテナで運ばれています。ペットフードも一般的にはドライコンテナで運ばれています。
混載便はドライコンテナが一般的です。
リーファーコンテナとは
温度管理ができるコンテナです。冷蔵や一定温度を保って運ぶ物資に使用します。価格は輸送量にもよりますが20フィート一本なら倍近い価格になることもあります。出荷できる港も限られ、混載はできないと言ってもいいので、基本一本で借りることになります。
リーファーコンテナは内部の温度を一定に保つことができるメリットもありますが、コンテナ開封時に外部との温度差で結露が生じてしまう場合があるなどの問題もあり、取り扱いに注意しなければいけません。このため、ドライ製品を扱う工場ではリーファーコンテナを使用する場合は商品の品質を担保しないという工場もあります。
保管について
ペットフードは常温保存商品としてある程度一定の温度が保たれている倉庫が好ましいですが、温度管理がされた倉庫もあれば、出入りも多く密閉されていない倉庫、雨風にはさらされないながらも外のような環境の倉庫もあります。
保管環境まで公開しているメーカーがありますので参考にしてみるといいでしょう。
参考までに弊社の倉庫はコンテナトラックが複数台入ることができる大型施設で、貨物の積み下ろしも倉庫内でできるようになっており、温度はある程度一定に管理された環境です。
パッケージについて
世界では一般的な空気穴(ピンホール)
海外ではパッケージに針で穴を開けたような空気穴が空いているものが一般的に存在ます。これは積載された時や温度変化、気圧によって袋が破裂しないようにするためです。商品は梱包されたり、重ねられたり、陳列したりする際には袋を潰す方向にしか力が働かないため、空気は出て行くだけで入ることはほとんどないという考え方で空気穴が採用されています。
最近はピンホールだけではなく、逆止弁の付いた専用のプラスチックのホールを付けているメーカーも見られます。
日本の湿気について
欧州から輸入されるペットフードは海上輸送時に赤道を二回通過しますし、日本は湿気の多い国ですのでピンホールのあるパッケージは適しているとはいえません。
湿気対策という面からもピンホールのない密閉された商品を選ぶことをおすすめします。
安価なペットフードの安全性について
安価なペットフードの安全性について考えてみましょう。
安価なペットフードに使われやすい原材料
安価なペットフードの場合、穀物やミール類が主要原材料となっている場合が多いでしょう。原材料は価格にダイレクトに反映される部分なので安価に作る場合は避けられない点です。
安価なペットフードに使われやすい添加物
合成保存料
自然由来のトコフェロールやクエン酸などではなく、合成保存料を使用しているものが多い傾向にあります。
合成保存料は決められた範囲で必要な分だけ使用されているので、極端に問題視する必要まではないと思います。
着色料
着色料は見た目を華やかにすることの他に、安心感を追加する目的で使用されます。
食材は自然由来のため、収穫時期などによって色に違いが生じます。また製造時の火加減など微妙な変化でも色に違いが生じます。出来上がった商品には問題がなくても色が違うと相談やクレームになることが多く、毎回同じ色を保つことは消費者の安心感につながるという面があります。
このため着色料は飼い主向けといった側面が強いものですので使われていないものを選ぶと良いと思います。
食材の生産地について
中国産の食材は安価なため、安価なペットフードは中国産の食材を使用している商品も多くもあります。
中国産の食材が安全ではないというわけではありませんが、過去の事例からも気にしておきたい点のひとつです。