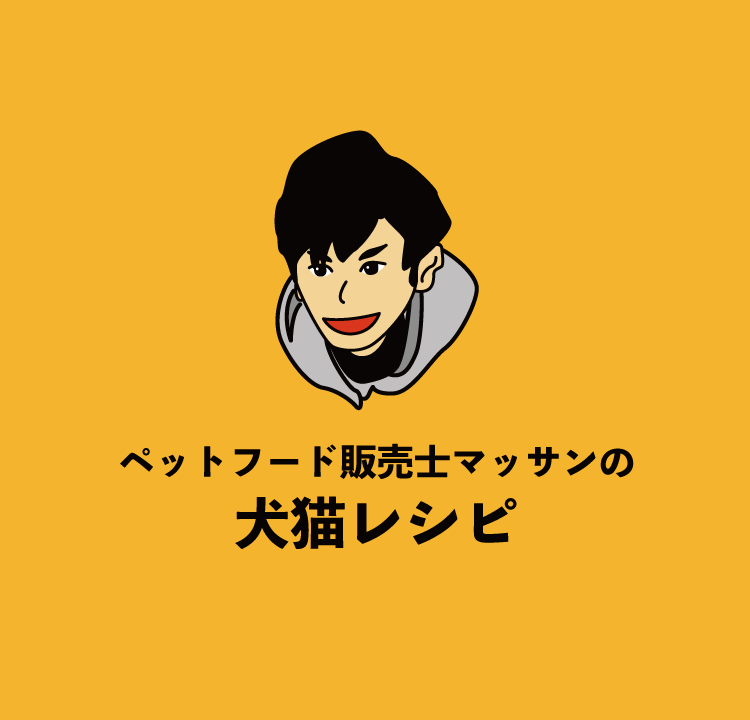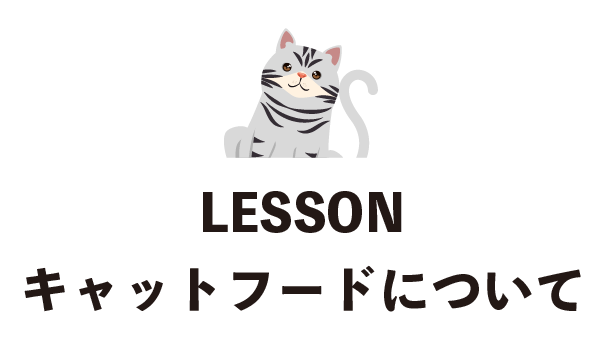目次
カルシウムは1%の働きが大切
骨粗鬆症という言葉も一般的になり、カルシウム摂取の意識は高まってきていると思います。カルシウムは主に骨や歯を作る成分として認識されています。実際にカルシウムの99%が骨や歯の構成成分として働きます。
しかし残りの1%にも非常に大切な働きがあります。

カルシウムには他の働きもあるんですね!
残りの1%で筋肉の収縮、神経の興奮の調整、ホルモン分泌、血液凝固といった大切な役割があります。この役割を見ると気付くことがあるのではないでしょうか。

神経の興奮の調整ですね!イライラした時はカルシウムを食べてといいますよね!
高カルシウム、低カルシウムの症状
低カルシウム(7mg/dL位)の場合はイライラしたり、食欲不振、下痢、嘔吐、脱力や、ふるえを起こす場合があります。酷いときには呼吸停止、QT間隔延長が起こります。
高カルシウム(15mg/dL位が1~2か月続く)の場合は元気がなくなり、食欲不振、下痢、嘔吐、神経過敏、多飲多尿、膀胱結石、酷いときには腎不全、QT間隔延長が起こります。

カルシウムは高くても低くてもいけないものなんですね。
そのカルシウムを狭い範囲内でコントロールしているのが喉にある1mm程度、大きくても4mm程度の上皮小体です。上皮小体は全部で4つあり、小さいにも関わらず立派な臓器です。
この上皮小体がPTH(副甲状腺ホルモン)を出し、カルシウムとリンのバランスを保っています。
カルシウムは与えればいいというものではない
カルシウムを多く与えると骨が異常発達し、骨の端が早く閉鎖することで関節が曲がったり、足が異常な方向に向いたりします。
このようにカルシウムは人間では健康食のように聞こえる一面もありますが、犬や猫にとってはバランスが非常に大切な成分です。
リンの効果
リンも8割は骨や歯の構成成分となり、残りが筋肉、脳、神経に存在しています。体液のpH調節を行ったり、エネルギー代謝にも関与しています。
リンは骨からカルシウムをひっぺがす!?
PTH(副甲状腺ホルモン)は骨からカルシウムを取り出して血中カルシウム量を上げ、リンを腎臓で排出して血中リン量を下げることでカルシウムやリンの血中濃度を調節しています。
このため血中にリンが多くなるとリンを体外に排出しようとPTHが機能して、骨からカルシウムをひっぺがすことでどんどん骨がもろくなってしまいます。
こうした理由を含む、副甲状腺ホルモン分泌が過剰になった状態を上皮小体亢進症といいます。

カルシウムを取っているつもりでも、リンが多ければ骨がもろくなってしまうんですね…
猫が肉食だからと肉だけ与えると骨がもろくなる
肉にはカルシウムが少なく、リンが多いので高リン血症になってしまいます。
その割合は推奨カルシウム:リンが1~1.5:1といわれているバランスに対し、肉や臓物ばかりを与えていると、1:16~35ととんでもなくリンが多くなります。
結果、骨がもろくなってしまいます。

手作り食の場合、肉を多めに与えて栄養バランスが取れていなかったら注意ですね。
キャットフードではバランスは調整されていますので、心配することはありませんが、手作り食の場合には注意が必要です。
以下の記事も是非参考にしてみてください。
ラバージョー
腎臓を患い、長期の腎不全の結果、高リン血症、低カルシウム血症となり、結果的に上皮小体亢進症を起こし、骨からカルシウムをどんどん放出することで、顎の骨がゴムのように柔らかくなってしまうラバージョーと呼ばれている状態があります。
このようにカルシウムとリンのバランス、甲状腺ホルモンの働きは犬猫の健康に大きな影響を与えています。
まとめ
- カルシウムは骨や歯を構成する成分
- カルシウムはホルモン分泌や血液凝固など多くの役割を担っている
- リンの80%は骨や歯を構成する成分
- リンは体液のpH調節を行ったり、エネルギー代謝にも関与
- 肉だけ与えると高リン血症になり、上皮小体亢進症を引き起こす
- 手作りフードの場合はカルシウムとリンのバランスに注意

キャットフード・ドッグフード選びではカルシウムとリンのバランスについて気に掛けている飼い主さんも多いと思います。どちらも適量を保つことが大切です。
特に猫が肉食だからと手作り食で肉だけを与えたりしないように注意しましょう。