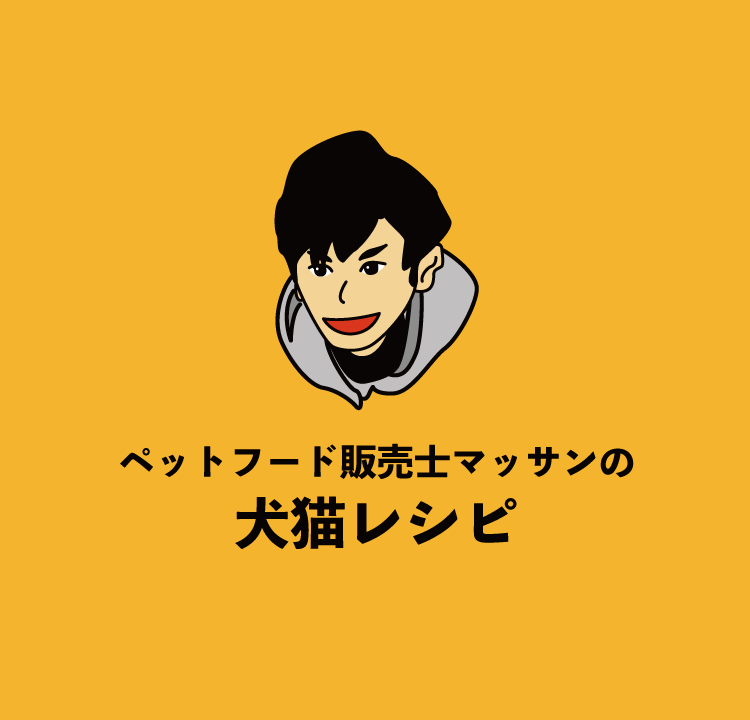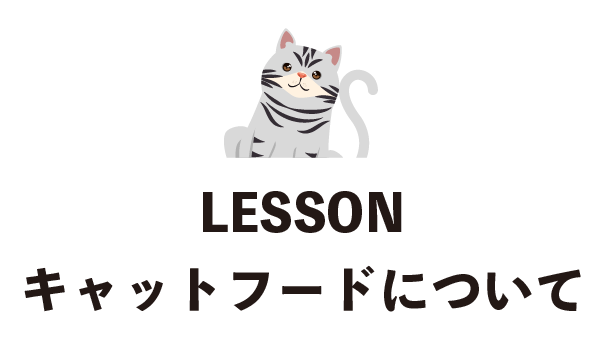目次
ヒューマングレードとは
ヒューマングレード(Human Grade)はここ数年で増えた表記で、日本では「人間が食べることのできる品質」という意味で使われています。

「ヒューマングレードの原材料を使用し~」とかよく書かれていますね!
日本語は巧みなので非常に便利な言葉のように使っていますが、ヒューマングレードという言葉には定義がなく、なにを表すかが定まっていません。また海外ではヒューマングレードの表記は”食用として人が食べることができる”という誤解を招くため、推奨されていません。
工場によっては人間が食べられるのかの問い合わせなど、後から問題が起こることを避けるために表記自体を禁止している工場もあります。
食用の定義
基本的に食用の場合、Human Edibleもしくは単にEdibleという言葉を使います。
人間の食用とは人間が食べるのに適したもので、安全確保の為のプロセスを全て合格したものと定義されています。

米や肉、魚とかインスタント、お菓子、フルーツとか人の食べ物全部ですね!
ヨーロッパではヒューマングレードという言葉も人の食用の基準を満たした場合に使用すべきという考え方が一般的であると欧州の関係者に確認しています。
キャットフード・ドッグフードは人間が食べるようには作られていない
キャットフード・ドッグフードはあくまでペットが食べるものであって、人の食用としての基準は満たされていません。
このためキャットフード・ドッグフードにヒューマングレードという言葉を使用することは、基準に則って人間が食べられるように製造したものと誤解される可能性が生じます。
ヒューマングレードという表記があっても製品の質は保証されない
ここが非常に重要です。ヒューマングレードという表記はとてもいいもののように見えますが、法による定義があるわけではないので、ヒューマングレードがなにを表すかが定まっていませんし、製品の安全性に影響を与えません。
つまり「原材料はヒューマングレードですか?」この質問に答えるためにはヒューマングレードがなにかを定義する必要があるわけですが、定義されていません。
飼料要件にも関係がないので、法的な根拠がないので「ヒューマングレードという言葉が使われていることと高品質であるかは別のこと」と考えた方がいいと思います。
このためヒューマングレードというよりも、人が食べられる原材料を使用しているといった具体的に書かれている方が明確に伝えていると言えるでしょう。
本物のヒューマングレードは非常に少ない
中には人の食用の基準をクリアした、人が食べることのできる本当のヒューマングレードの商品もありますので、ヒューマングレードという言葉の使用は禁止されたりはしていません。
優秀な日本語のグレーゾーン
日本語は非常に優秀で、察することができる人種です。同じ表現でも違う言葉がたくさんあり、言葉から雰囲気もしっかり掴むことができます。

優しい味と言っても外国人は伝わらなそうですね?
このように日本人はヒューマングレードという言葉が書かれているキャットフード・ドッグフードをみたら「高品質なのかな?」とは思っても、目くじらをたてて「キャットフード・ドッグフードを人が食べていいと誤解するぞ!」という人は少ないと思います。
しかし海外では書かれていることを直接的に受け取る部分があり、法律でもしっかり決まっているので、表記には気を遣っている印象があります。
日本では表示に関する法律をあれこれ確認しながら、その中で雰囲気を伝える表記もしている印象です。

そんな言葉のひとつがヒューマングレードかもしれませんね。
人が食べられる食材が支持されることによる弊害
最近は人が食べられる食材を猫にも与えたいという風潮が強くなり、肉副産物を与えることが悪いことにようになってきました。
肉副産物は人間は好んで食べないものの、栄養があって食べられるもので、人と猫が食において競合せず、なおかつ資源を有効活用でき、更に価格も抑えることができる方法のひとつでした。
例えば、猫の缶詰めには栄養も豊富な魚の血合い肉を使用していましたが、見た目が黒っぽいため、人間が食べる白身部分を使用する傾向が強くなっています。
こうして人と動物の競合が始まり、食材の価格もあがり、人の食材もキャットフード・ドッグフードも価格が上がり始めています。
このように、限りある資源を無駄にしない方法も今後の課題のひとつです。
まとめ
- ヒューマングレードは定義がない言葉
- キャットフード・ドッグフードに表示することは海外では余り良しとされていない
- 人間が食べられるものを猫にも与える風潮により、資源の有効活用の形が崩れつつある

ヒューマングレードという言葉について、日本と海外では考え方が違うんですね。キャッチコピーになるか紛らわしい言葉になるか、難しいところですね。
また、資源という点からも人と動物がうまく共存できる世界が作れるように、飼い主ひとりひとりが意識することも大切かもしれません。