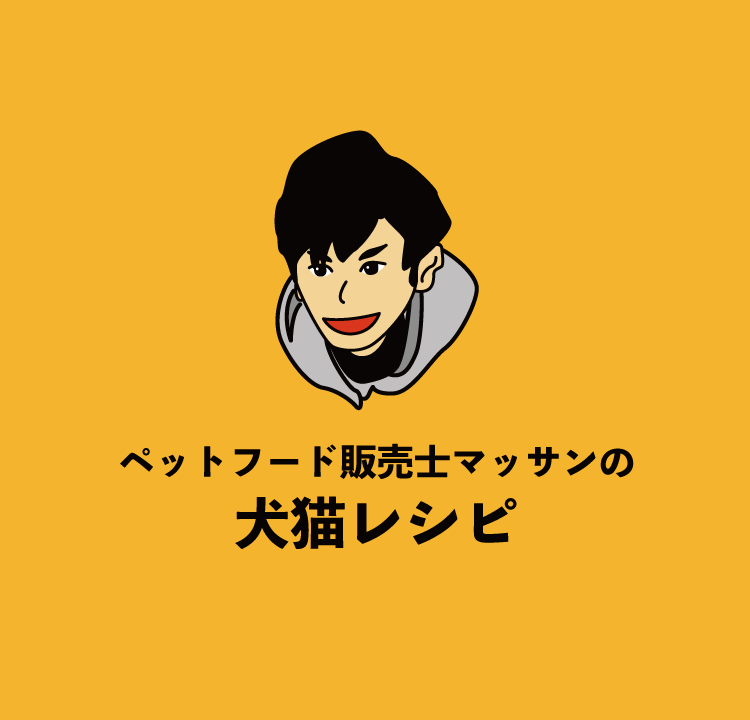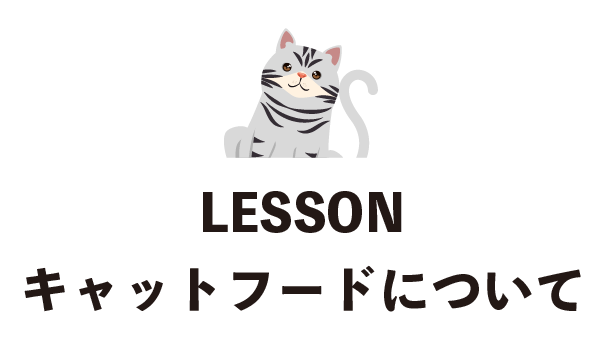目次
グレインフリーキャットフードとは?
グレインフリーキャットフードとは、穀物を使用していないキャットフードのことです。
猫は植物を消化することが苦手な動物です。このため穀物を使用しない、より猫の生態に近づけた食事を求めた結果、グレインフリーというレシピが生まれました。
動物性タンパク質が豊富
グレインフリーキャットフードの特徴は穀物の代わりに、肉原料が豊富に含まれていることです。これにより動物性タンパク質が豊富になります。
人は炭水化物からエネルギーを作り出ししますが、特に猫はタンパク質からエネルギーを作り出すことができるため、品質の良い動物性タンパク質は猫にとって有益です。
消化吸収率が高い
動物性食品を多く使用することにより、セルロースなどの食物繊維を多く含む植物性食品が多いフードと比較して消化吸収率を高くすることができます。
ミネラルの消化吸収に有利
例えば鉄の場合、動物性食品にはヘム鉄、植物性食品には非ヘム鉄が含まれています。ヘム鉄は還元型でそのまま活用ができるのに対し、非ヘム鉄は還元しなければ活用することができません。還元するためにはビタミンCが必要ですが、ビタミンCは銅の吸収を抑制してしまいます。
このように肉食動物にとってより自然な形で摂取するためには、できるだけ動物性食品からミネラルを摂取することが望ましいと考えられます。
穀物の代わりに芋類がよく使われる
穀物の代わりに原材料として使われるのが「肉類」と「豆類」と「芋類」のジャガイモやサツマイモです。
炭水化物は猫にとって不必要な栄養素ではないと考えられているので、適量含まれている分には問題ありません。しかし猫は炭水化物を一定量は消化することができますが、多くを消化できる構造にはなっていないため、あまり多すぎると消化器官に負担をかけてしまいますので、配合量が重要です。
炭水化物の含有量には定めがない
実はペットフードには炭水化物の含有量は定めがありません。あくまで私の見立てではドライフードで考えると、40%程度に抑えられていれば問題がないと考えています。
穀物アレルギー対策
穀物が原因となるアレルギーは決して多くありませんが、なかでも小麦はアレルギーの元になる可能性がやや高めです。アレルギーの原因はタンパク質なのでそれだけタンパク質が豊富な食材とも言えます。

キャットフードなのにアレルギーが出ることがあるんですね!
人間も穀物やそば、シーフードなどでアレルギーが出る方もいますので、食べられるからアレルギーが出ないわけではないのは猫も同じです。
注意してほしい点はグレインフリーだからアレルギー対策になるわけではないという点です。
アレルギーはタンパク質が原因のため、穀物よりも猫本来の主食である鶏肉や魚でアレルギーが出るケースの方が多いです。更にいえばノミや花粉などの方が食品アレルギーよりも多くなります。
上記からもあくまで穀物アレルギーを疑う場合はグレインフリーキャットフードを活用してみてください。
嘔吐改善
原材料に穀物が使用されているキャットフードはグレインフリーキャットフードと比較して摂取量が多くなる場合がほとんどです。
単に食べる量が多くなるので胃腸に負担をかけたり、刺激して嘔吐に繋がっていたということもあります。
穀物に「豆類(大豆)」を含むか含まないかは国の認識で違う
これもまた重要な点ではありませんが世界的な定義から考えるとこんな考え方もあります。
実は「穀物」には「豆類を含むか含まないか」という2種類の見解があります。
そもそも穀物という定義がわかりにくい部分があり、日本では「穀物」に狭義では豆類を含まず、広義では豆類を含むとしており、見解がわかれるところです。
しかし世界的には穀物に豆類は含んでいません。このため多くのグレインフリーといわれているキャットフードには豆類が使われています。しかし豆類を使用していても、大豆は使わない商品は多いです。
使われている豆類はほとんどエンドウを使用
例えばグレインフリーと宣伝しているジャガー、ニュートロ ナチュラルチョイスの穀物フリー、オリジン、ウェルネス コア、NOW(ナウ)、go!、アカナ、ヤラー、ティンバーウルフ、ソリッドゴールドもグレインフリーとして販売されていますが、豆類が含まれています。
そしてそのほとんどがエンドウを使用しています。豆類の中でも大豆はアレルゲンになりやすいので注意が必要ですが、エンドウは低アレルゲンで豊富なタンパク質を含んでいるためです。
アレルゲンとしてはエンドウより鶏肉などの方が強い
低アレルゲンでもアレルゲンだと考えた場合ですが、むしろ鶏肉など主原料のアレルギーの相談の方が多いです。
三大アレルギーの大豆アレルギーと、エンドウアレルギーは全くの別物。エンドウ豆は乳児でも食べられる食材です。豊富なタンパク質、食物繊維として配合されていることがほとんどです。
猫の体の作りについて
猫は「穀物の消化が得意ではない内臓の作り」になっています。理由は猫の消化器官の作りが雑食の人間や犬とは構造が違うからです。
猫は大腸が短い
猫は大腸の消化管が身長の4倍程度しかなく、雑食・草食動物に比べてかなり貧弱です。これによって穀物など植物が消化しにくくなります。
盲腸がほとんど残っていない
草食動物は盲腸が非常に発達していて植物由来のセルロースを分解することができます。
しかし猫には盲腸がほとんどないため、セルロースなどを消化吸収することができません。多少はすい臓で消化、吸収できますが、唾液など他で消化吸収できていないため、負担が大きくなります。
乳糖を多く消化できない
猫の内臓は炭水化物や牛乳に多く含まれる乳糖(ラクトース)は大量に消化できない構造になっています。炭水化物を多く与えると下痢や不調を招く原因になることがあります。
タンパク質からエネルギーを作り出せる
猫は小腸が発達し、動物性タンパク質や脂肪の消化吸収に向いている作りとなっています。さらに猫の肝臓は窒素化合物を分解する酵素の働きが非常に高く、タンパク質をエネルギー源の一部として使うことができます。
穀物による血糖値の上昇のリスクについて考える
穀物を摂取することによる血糖値の上昇について学んでおきましょう。
オリジンにペットフードオブザイヤーなどの認定を行っているGlycemic Research Institue®での見解が参考になります。
「ペットフードには高血糖成分を避けるべきである」という見解が示されており、穀物はペットフードの成分としては血糖を上げる食品であるので避けるべきであると考えられています。
トウモロコシや穀物の摂取は、犬や猫だけでなく、人間の血糖値にも直接影響します。高血糖成分は血糖値を過剰に上昇させ、てんかん、甲状腺機能低下症、アレルギー、イースト菌感染症、癌および糖尿病のリスクを高めます。犬用及び猫用のペットフード中の一次(高)レベルの高血糖穀物は許容できません。これらには、小麦、トウモロコシ、米、玄米も含まれます。
出典:Glycemic Research Institute®
こうした見解がありますので、穀物については飼い主自身で使用の有無を考えられると良いかと思います。
合わせてこちらの記事もご参考いただけましたら幸いです。
まとめ
- グレインフリーとは猫の内臓の作りに合わせたレシピ
- 動物性タンパク質が豊富
- 消化吸収率が高い
- しなやかで強靱な体作りに役立つ
- ミネラルの消化吸収に有利
- 血糖値上昇のリスクに配慮

グレインフリーのキャットフードがまだまだ多くはないという点が驚きです。穀物の血糖値を上げてしまうという点については考慮してみてもいいのかもしれません。