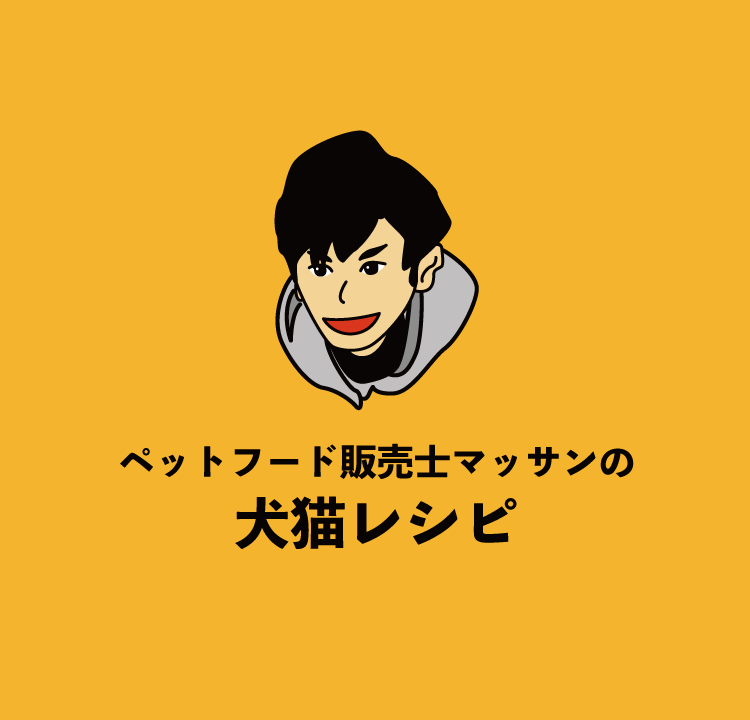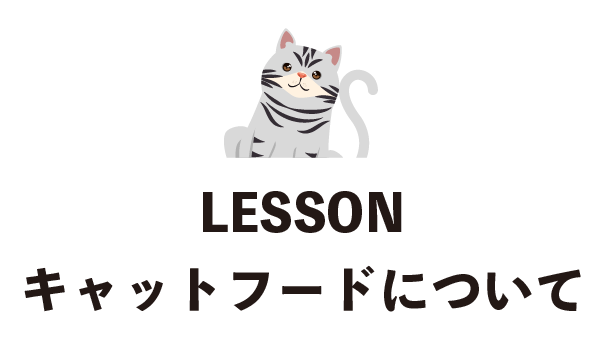目次
ペットフード選びでチェックしたい項目は?

キャットフードやドッグフードには色々な原材料が使われていて、どこを見ればいいのかわかりません。
今回はペットフード選びで悩んだ時に最初にチェックする項目について紹介します。
- 主要原材料
- タンパク質含有量とリン含有量
- 炭水化物含有量
- 米・小麦・トウモロコシなどの穀物の配合
- カルシウム:リン:マグネシウムのバランス
- 低GI食材を使用している製品を選ぶ
- ミートミール・ミートボーンミール
- 動物性油脂
- 食品添加物に発がん性物質
キャットフード、ドッグフードを購入する際には以上ような項目を確認するとよいと思います。
主要原材料
まずは愛犬、愛猫が好む食材が使用されているかと確認するとよいと思います。
ペットフードの場合は犬や猫の生態に合わせて肉原材料が多く使われています。以下の様な食材が多いと思います。
- 鶏肉
- 牛肉
- 豚肉などの肉類
- マグロ
- サーモンなどの魚類
一番ベーシックなものが鶏肉で、犬も猫も好んで食べ、比較的好き嫌いの少ない食材です。
鶏は育てやすいこともあり、価格が安定しているため、ペットフードに使いやすいという理由もあります。
魚の場合は国内産ではマグロやカツオ、海外産ではサーモンや白身魚が多いです。
ここ数年は魚の価格が非常に高騰しており、サーモンも高級魚となってきました。また、魚は水分含有量が多く、調理後は肉よりも少なくなってしまうため、より多くの量を必要とします。
このため、特に魚系のペットフードは値上がりしている傾向にあります。
タンパク質とリン含有量
ドッグフード、キャットフードは肉原材料を多く含むため、タンパク質が多い傾向にあります。
犬も猫もタンパク質を必要とする生き物ですので、特に動物性由来のタンパク質が多いペットフードが好まれます。
特に猫はタンパク質からエネルギーを作り出すことができるので、より高タンパク質食が向いています。
ただし、タンパク質の構成成分にリンがあります。リンの過剰摂取は腎臓にも影響しますので、高タンパク質でもリンが抑えられているペットフードがおすすめです。
炭水化物含有量
ペットフードには炭水化物の表示義務がありません。とはいえ、タンパク質、脂質、繊維、灰分、水分の成分割合は表示義務がありますので、これらを100%から引くことで簡易的に炭水化物を求めることができます。
例)100%-タンパク質(36%)-脂質(20%)-繊維(3%)-灰分(8.5%)-水分(9%)=炭水化物(23.5%)
適度の量ですが、特にキャットフードには30~40%程度までがいいのではと言われています。また猫の嗜好性は高くありません。
犬は雑食寄りの肉食ですので炭水化物量は猫ほど気にする必要はありません。
キャットフード・ドッグフードの炭水化物について。犬はエネルギー源に、猫はデンプンの消化吸収が苦手ですが全く不必要ではない
米・小麦・トウモロコシなどの穀物の配合
犬は人と長いこと暮らすことによって随分植物を消化吸収できるようになっていますが、猫は穀物を消化することが苦手です。
そして食品に含まれているミネラル、例えば鉄分などは動物性食品に含まれているヘム鉄は還元型でそのまま活用することができますが、植物性食品に含まれている非ヘム鉄はビタミンCなどで変換しないと活用することができません。しかしビタミンCは銅の吸収を妨げたりと他のミネラルにも関係してしまうため、できる限り動物性食品から摂取することが大切であると考えています。
このため穀物が含まれていない、もしくは少量のものを選ぶことがおすすめです。
原材料表示は内容量の多い順に書かれていますので、米・小麦・トウモロコシが上位表示されているキャットフード、ドッグフードは控えてもいいと思います。多いものだと1番目に表示されているものもありますし、肉類に続いて2番目に表示されている商品も多いのが現状です。
穀物が含まれている理由はいくつかあります。
- 植物性タンパク質など栄養源として
- 米を使用することによって低アレルゲンフードを作る
- 穀物は価格が安定している傾向にあるので、安全に安価なキャットフード、ドッグフードを作るために必要
植物性タンパク質など栄養源として
最近植物性タンパク質も動物性タンパク質も変わらないのではという話も出てきていますが、植物性タンパク質の20%はアンモニアになってしまうため、肝臓に病気のある動物は動物性タンパク質の方がいいとされています。穀物を食物繊維として配合するという考えはありませんが、配合量が多いので結果的に食物繊維の配合量に影響するという部分もあります。
米を使用することによって低アレルゲンフードを作る
様々な食品のタンパク質がアレルギー源とあるわけですが、加水分解タンパク質にすることでアレルゲンになりにくくなります。中でも加水分解した米タンパク質はアレルギー対応食によく使用されます。
肉などよりも価格が安く安定もしているので、安全に安価なキャットフード、ドッグフードを作るために必要
穀物は安いから嵩増しに使うなんて声もありますが、よほど安い穀物を使用しない限りは穀物もそれなりに価格がしますので、最初から嵩増しとして考えることはないと思います。単にメーカーの希望販売価格に合わせて原価を調整するために使うということはあります。
米など穀物は流通量が安定しているので価格も安定している面があり、原材料としては非常に使いやすいという一面があります。
低GI食材を使用している製品を選ぶ
GLYCEMIC RESEARCH INSTITUTE®での見解を例に紹介したいと思います。
ペットフードの血糖において禁忌とされているものが下記の高血糖穀物として紹介している4種です。中でも特にトウモロコシについて言及されていますが、これら4種は禁忌(CONTRAINDICATED )であると紹介されています。
それに追加して高血糖炭水化物が紹介されています。この中で特に避けたいものはポテトスターチであると紹介されています。
高血糖穀物
- 小麦
- トウモロコシ
- 米
- 玄米
高血糖炭水化物
- ジャガイモ
- ポテトスターチ
- ビート
- 調理されたニンジン※1
※1 cooked carrotsが何を表すか具体的にわかりませんでした。
ここで注意して欲しい点は、これらが入っているから必ずしも製品自体が高GIとは言えないということです。
ジャガイモについて
ジャガイモについては「それ単体で高GIであるが、ペットフードや人の食べ物にジャガイモをただ含めるだけで血糖指数と負荷が決まるわけではない」と記されています。
使用するタンパク質の種類に重点を置き、タンパク質と炭水化物と脂肪の比率(the protein-carb-fat ratios)によって決まるとされています。高品質のタンパク質を十分に含んでジャガイモの含有量が低い場合は血糖の反応は鈍化するとされています。
また、サツマイモはグリセミックインパクト(おそらく血糖値上昇に与える影響という意味だと思います)が低いので、ジャガイモの代替品になるとのことです。
玄米について
上記では玄米が上げられていますが、玄米のGI値は約55で白米の約77と比較すると低GI値です。
低GI値は55以下の食品を指すため、玄米は高GIに分類する必要はないのではと思います。
カルシウム:リン:マグネシウムのバランス
犬猫に多い病気のひとつに尿路結石がありますが、これを予防するために、カルシウムとリン、マグネシウムの比率が概ね1.2~1.5:1:0.1~0.08程度であることが重要です。これは療法食など予防の場合なので、理想はカルシウムとリンが1.2~1.5:1位とややカルシウムが多いほうが理想です。
男の子の方が女の子に比べると詰まりやすいと言われています。なりやすい割りにとても危険な病気で、尿毒症が発症すると数日で亡くなることもあります。

カルシウムとリン、マグネシウムのバランスがいいと尿路結石を予防しやすいのですか?
それではカルシウム、リン、マグネシウムの関係についてお話をします。
リンとカルシウムは結合することでリン酸カルシウムとなり、これが骨の主成分になります。一番重要な点はこのバランス。理想は1.2~1.5:1位と少しカルシウムが多いほう良いようです。
カルシウムよりもリンが多い場合、血中のバランスをとるために骨からカルシウムを取り出してしまうことがあります。これでは骨の主成分であるリン酸カルシウムを作る意味がありませんね。
マグネシウムに関しては、余分なリンが尿として排出されると、同じく排出されたマグネシウムと結合してストルバイト結石の原因になる場合があります。

成分表を見るとリンが多かったり、マグネシウムが多かったり、いいバランスの製品って少ないですね・・・
魚を豊富に含む製品の場合はカルシウム、マグネシウムが多くなりがちなので注意が必要です。多くがこのバランスはうまく取れていないのが現状です。
なぜカルシウム:リン:マグネシウムが1.2:1:0.08位がいいのか
各工場などによってAAFCOの発行年の適用年が違いますので、見解には若干のずれがみられますが、私は以下のような話を確認しています。
現在AAFCO2016年度版(4000kcal ME/kg前提)が最新ですが1997年度版(3500kcal ME/kg前提)を採用しているメーカーがあります。ひとまずこの場では2016年度版でお話します。
まず、上で紹介した通り、カルシウムとリンは相互関係があり、1.2~1.5:1位がよいと言われています。これに加えてAAFCO2016年度版ドライを確認頂きますと、マグネシウムの値が導き出されます。
成長期の猫でカルシウム:リン:マグネシウムは最少量換算で1.0%:0.8%:0.08%となっています。
成猫では0.6%:0.5%:0.04%となります。こちらは比率で考えますと1.2:1.0:0.08となります。

幼犬幼猫、成犬成猫ともにバランスで考えるとほとんど同じなんですね!
注意点としては猫の場合にマグネシウムの値には但し書きがあり、猫の平均尿ph値が6.4以下でない場合、食事のマグネシウムの値が増加するとストルバイト結石になる可能性が高くなるとされています。
If the mean urine pH of cats fed ad libitum is not below 6.4, the risk of struvite urolithiasis increases as the magnesium content of the diet increases
こうした観点から主にマグネシウムは最低量の0.08から1.0位を基準に考えられています。
カルシウムはリンともマグネシウムとも相互関係がありますので、ここから逆算すると概ね、カルシウム:リン:マグネシウムの値が1.2:1:0.08位になるという考えのようです。
ストルバイト結晶の予防を考えてマグネシウムの最小値換算から換算していますので、カルシウムは1.5位まで増えても問題なさそうです。
カルシウム:マグネシウムが2:1
カルシウムとマグネシウムは2:1で摂取した方がよいという考えがありますが、マグネシウム0.08%の方に合わせるとカルシウムが0.16%と少なすぎます。カルシウムに合わせるとマグネシウムが0.6%と多過ぎてストルバイト結晶の可能性が高まります。
マグネシウムは100kcal中0.19g-0.35gが良いかもしれない
最近はペット栄養学会などで、マグネシウムの値が100kcal当たり0.09g-0.018g位だとシュウ酸カルシウムになりやすいのではないか、0.019g-0.035g位がいいのではないかと言われてきています。
これをパーセントに直すと、例えばロニーの場合だと410kcalですので、0.37-0.07%だとシュウ酸カルシウムになりやすいのではないか、0.08-0.15%位がいいのではないかということに置き換えられます。
マグネシウムの値を上げるのであれば、カルシウム、リンも上げる必要があると考えられ、調整が必要になってくるため、フード製造上では長年問題がないとされてきた実績のある値が重要視されつつ、徐々に変更が適用されるようになっています。
こうして私は上記バランスにて紹介させて頂いております。
この辺はAAFCOの新バージョンなどが出ることで、徐々に変わっていくかもしれませんね。
ミートミール・ミートボーンミール(肉骨粉)には注意
今までは配合されていても健康には問題のない原材料でしたが、ここからは注意すべき点となってきます。

市販されているペットフードなのに注意ですか?
現状は法整備も進み、原材料に対する目も厳しくなってきていますが、ミートミールと表記される原材料は気にかけておきたいところです。
簡単に説明すると、ミートミールはAAFCOの定義では「血液、毛、蹄、角、皮、糞尿、胃、及び第一胃の内容物を除いた、哺乳動物組織から得られるレンダリングされたもの」で、つまり哺乳動物ならなんでもいいということになります。

本来食べれないものは混ざっていないんですね。
AAFCOの定義に沿っていれば「血液、毛、蹄、角、皮、糞尿、胃、及び第一胃の内容物を除いた」ということなので、食べられないものは入っていません。
ただしこれは法律ではないので、沿っていないことも考えられないわけではありません。酷い話では病気で亡くなったり、死後腐敗が進んだ鳥をまぜこぜに粉砕して原材料とすることもあるといいます。(実際に自分の目で確認はしていません)
また、肉骨粉には注意が必要です。
肉骨粉は高温で処理するためにウイルスなどは死滅しますが、狂牛病の原因となったプリオンはたんぱく質だったため死滅せずに広がってしまったということがありました。
動物性油脂の危険性
動物性油脂は死んでしまった様々な動物を粉砕して精製した脂であったということがありました。死んだ動物や副産物から脂を取るという行為は、過去には一般的で実際に行われていたことです。
その中に病気で亡くなった動物も混ざっていたら?糞便も全て?そう考えると非常に怖いものに見えてきます。

なぜ動物性油脂を使うのですか?
- エネルギー源として優れている
- 嗜好性を高める
- 脂溶性ビタミンの九州を高める
- 必須脂肪酸の供給源
上記のような理由があります。また、ドライフードは油脂がないとボソボソになります。ドライフードの形(四角や丸)にするために肉自体に含まれている油脂や別途加える油脂も含むことで成形(ツナギのような作用)されます。
ただし動物性油脂が悪いのかというとそういうことではなく、例えば原材料が特定できる場合は明確にして示すと良いとされていますので、鶏からのみ作っているのであれば鶏脂と表記されます。牛であれば牛脂ですね。
原材料が特定できるからといって、上記のすべての問題が解決されるワケではありませんが、動物性油脂自体はペットフードに必要な原材料のひとつですので、このように原材料が特定できる表記の製品を選ぶと良いかと思います。
食品添加物に発がん性物質
発がん性のある添加物についてはこちらでも話しましたが、簡単に話すと、そうした危惧のあるものにはBHA、BHTなどがあり、酸化防止剤として使われています。
BHA、BHTは食品添加物としては認められていますが、ともに発がん性があることが指摘されています。しかしBHAは前胃がない動物には発がん性の兆候は見られなかったと結論づけています。エトキシキンは人が食べるものへの添加は認可されておらず、農薬登録もされていない添加物です。

このご時世に発がん性物質が食品に入っているんですか??
そう思いますよね。しかしBHAの発がん性はわらびの3分の1、ふきのとうの2分の1以下と言われています。このように摂取する量の問題であり、研究結果として安全である値が取られています。このため、目くじらを立ててBHAやBHTがダメだ!というのではなく、必要に応じて使われていると考えるといいかと思います。
他の食品添加物も基本的には同じ考えです。
後は飼い主の考えによるものなので、例えば人よりも体が小さい犬であれば危険じゃないかという考えもあると思いますし、そうした飼い主の選択は尊重されるものと思います。気を付けておいて損はないかなと思いますね。