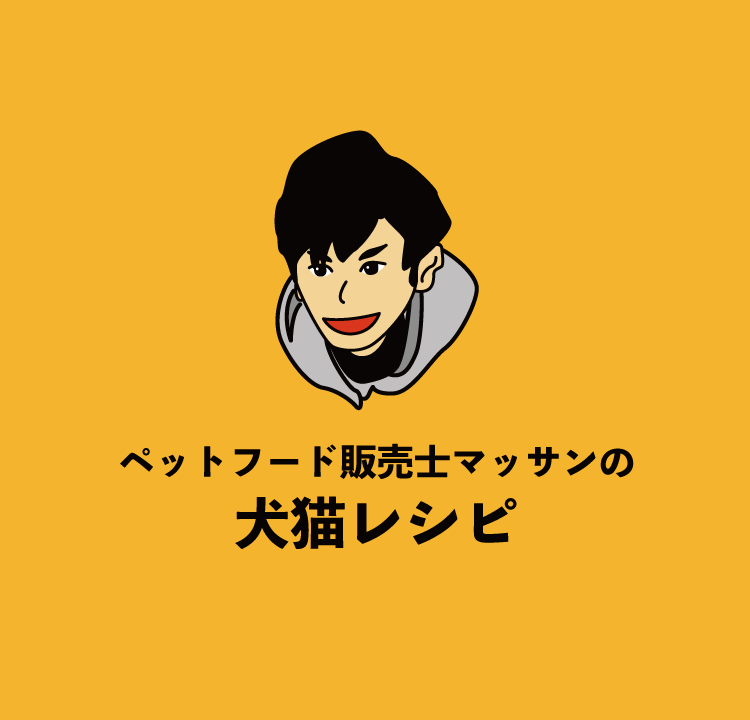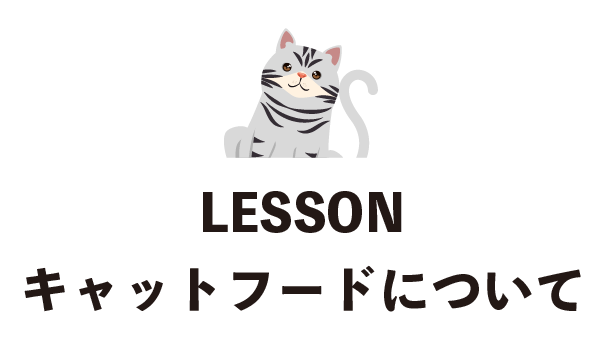目次
キサンタンガムとは?食品からペットフードへと広がる用途
キサンタンガムは、微生物由来の天然多糖類であり、主に「ザントモナス・カンペストリス(Xanthomonas campestris)」という細菌によって発酵生成される成分です。

微生物由来なのですか?
とうもろこしや小麦、砂糖などを原料とし、それを微生物が発酵することで得られる粘性のある物質がキサンタンガムです。これを精製・乾燥して粉末状にしたものが、食品やペットフードの増粘剤として使用されています。
人間用の食品でもドレッシングやスープ、冷凍食品、さらにはグルテンフリー製品などに幅広く用いられており、安全性の高い安定剤・乳化剤・増粘剤として知られています。食品添加物としての歴史は長く、日本国内でも食品衛生法に基づいて使用が認められている成分です。
このように、人間向けの食品で実績のあるキサンタンガムが、キャットフードやドッグフードにも使われるようになりました。
ペットフードにキサンタンガムが使われるの理由
ペットフードにおけるキサンタンガムの主な役割は、「テクスチャーと安定性の向上」です。
特にウェットタイプやピューレタイプ、半生タイプのフードでは、原材料同士を均一に混ぜ、滑らかな食感を保つために増粘剤が不可欠です。キサンタンガムはごく微量の使用で高い粘性を発揮するため、フードが分離せず、見た目も味も一定の品質を保つことができます。
さらに、水分と油分をうまく分散させる乳化作用や、加熱・冷却による品質劣化を防ぐ保形性も兼ね備えており、保存期間中も均一な状態を保てるのが特長です。
キサンタンガムの安全性
キサンタンガムはFDA(米国食品医薬品局)をはじめ、EU、FAO/WHOの合同食品規格委員会(Codex)でも安全とされており、世界中で認可されています。
摂取量について
しかしどんな食品添加物にも言えることですが、摂取量が重要です。キサンタンガムは食物繊維の一種であり、小腸で吸収されることなく大腸に届き、腸内細菌によって分解・発酵されます。一般的には便通を整える作用や腸内環境の改善に寄与することもありますが、体質など個体差によって過敏に反応する可能性もゼロではありません。
特に腸内環境が乱れやすい高齢犬・高齢猫や、胃腸の弱い個体、消化器疾患のあるペットには注意が必要です。まれに軟便や下痢といった症状が出るケースがあります。
キサンタンガムの原材料によるアレルギーの有無
キサンタンガムそのものに対するアレルギー報告はほとんどないのではないかと思いますが、キサンタンガムがどのような原材料をもとに発酵されたかが問題になる場合があります。
例えばとうもろこしや小麦などを基材に使用している場合、それらにアレルギーを持つ犬や猫にとってはアレルギー反応が出る可能性があります。
グレインフリーを選ぶ飼い主が増えている中で、キサンタンガムの原料表記が曖昧である場合は注意が必要です。「増粘多糖類」とだけ記載されている製品よりも、成分ごとに明記しているフードの方が、アレルギー管理の観点からは安心だと思います。
キサンタンガムの作り方(参考)
1. 原料の準備
キサンタンガムの原料は、主にグルコース(ブドウ糖)やスクロース(ショ糖)などの糖質です。これらはトウモロコシ、小麦、サトウキビなどの植物から獲得できます。グルテンフリー用途にはグルテンを含まない糖源が使用されます。
2. 発酵
キサンタンガムの本質は「微生物が糖を発酵して作る多糖体」であり、この過程が最も重要です。
- 使用される微生物はザントモナス・カンペストリス(Xanthomonas campestris)というグラム陰性細菌です。
- 滅菌された糖液にこの菌を加え、栄養源(窒素、リン、微量元素など)を含んだ培地で一定時間発酵させます。
- 発酵中にザントモナス菌は、糖を利用してキサンタンガム(高分子の多糖類)を分泌します。
- 発酵時間は24~72時間程度。温度は20〜30℃前後、pHは6〜7が一般的です。
3. 回収と精製
発酵液の中には菌体、未利用の糖分、キサンタンガムが混在しています。
- まずアルコール(エタノールやイソプロパノール)を加えて沈殿させることで、キサンタンガムを抽出します(沈殿工程)。
- 次にフィルタリングや遠心分離を行ってキサンタンガムを回収します。
- 得られた粗キサンタンガムは、さらに洗浄、脱水、乾燥されて不純物を取り除きます。
4. 粉砕と製品化
乾燥されたキサンタンガムは固形またはブロック状なので、用途に応じて微粉末化(パウダー化)され、製品として仕上げられます。必要に応じて他の安定剤やキャリア成分と混合されることもあります。
補足:ヴィーガンやグルテンフリーへの対応
製造に使われる糖源がグルテンを含まない場合、グルテンフリー対応のキサンタンガムとなり、アレルギーや特別な食事制限に配慮した製品として流通します。また、動物由来の原料を使用しないため、ヴィーガンにも適合します。
キサンタンガムの歴史とペットフード
キサンタンガムが初めて発見されたのは1960年代初頭で、アメリカの農務省(USDA)の研究によって、ザントモナス・カンペストリスという微生物が糖を発酵させることでこの特殊な多糖類を産生することがわかりました。その安定性・増粘力の高さから、すぐに食品工業向けの増粘剤や安定剤として注目を集め、サラダドレッシング、冷凍食品、ベーカリー製品などに使用され始めます。
特にアメリカでは1969年にFDA(食品医薬品局)により食品添加物としてGRAS(一般に安全と認められる)指定を受けたことで、食品用途での使用が加速。その後、世界各国でも同様に安全性が認められ、1970〜80年代を通じて加工食品業界におけるスタンダードな増粘剤の地位を確立しました。
ペットフードへの転用の流れと良さの見直し
1990年後半~2000年代にナチュラルなどを掲げるブランドが登場し始め、人間用に使われている成分や製造技術をペット向けにも応用する流れが出てきました。
ウェットタイプやパウチタイプのフードが増える中で、分離防止、保水性、乳化性を求める需要が高まり、従来の増粘剤(例えば寒天、カラギーナン、でんぷん類)と併せてキサンタンガムが採用されるようになります。特に食感を柔らかく、なめらかに整える能力が重視され、シニア用フードや嗜好性を重視した製品での使用が広がっていきました。
2010年代になるとペットフード業界全体で「無添加」「オーガニック」「グレインフリー」といったナチュラル志向が加速したことで、キサンタンガムなど増粘剤、添加物を警戒感を持つ方が増えてきました。
これによってキサンタンガムや増粘剤不使用という流れが一部で起こり、米粉や寒天などを使用して添加物フリーをアピールするようになってきます。
しかしキサンタンガム自体が天然由来かつごく微量使用で効果を発揮し、消化に大きな問題を起こしにくいことが再評価されるようになり、「安全な添加物のひとつ」として一定の支持を保ち続けています。
まとめ
キサンタンガムはプレバイオティクス配合フードなどでも意図的に入れられていることもありますし、無添加を至上主義とした場合には避けられる傾向にあります。
このように設計思想によって大きく変わっているだけのものともいえ、今後も適切な評価のもとで利用され続けていくと考えています。